|
第3節 災害応急対策 |
|
放射性物質の拡散又は放射線の影響から、住民の生命、身体及び財産を保護するため、町はできる限り早期に的確な応急対策を実施する。 なお、大規模自然災害と原子力発電所に係る事故等が同時期に発生した場合には、情報収集・連絡活動、モニタリング、屋内退避、避難誘導等の防護活動、緊急輸送活動等に支障が出る可能性があることを踏まえて対応する。 1 情報の収集及び連絡体制の整備 (1) 原子力事業所の事故により放射性物質又は放射線の影響が広範囲に及び、町が原子力緊急事態宣言に係る緊急事態応急対策実施区域になった場合、町は、緊急事態応急対策拠点施設(オフサイトセンター)に設置される原子力災害合同対策協議会へ職員を出席させ、原子力事業所の状況、モニタリング情報、住民避難・屋内退避等の状況とあわせて、国、所在県の緊急事態応急対策活動の状況を把握するとともに、町及び県が行う応急対策について協議する。 (2) 町は、県と連携を密にして情報の把握に努める。 2 通信手段の確保 (1) 町は、県と連携し、必要に応じ情報連絡のための通信手段を確保する。 ○特定事象発生時 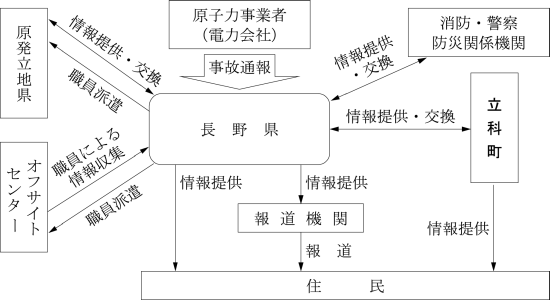
○原子力緊急事態宣言後 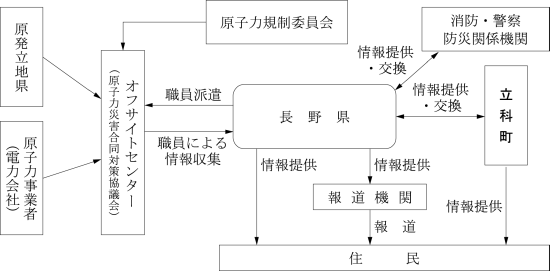
3 活動体制 (1) 職員の参集 ア 動員配備人員の一般的基準 動員・配備の基準については、第2編第2章第1節「非常参集職員の活動」に定めるところによる。 イ 注意配備 第一次警戒配備担当課長は、次に掲げるときは、担当職員に命じて、事故に関する情報収集及び情報提供を行い、第一次警戒配備に移行しうる体制を整える。 (ア) 原子力事業所の事故により放射性物質又は放射線の影響が広範囲に及び、町内において屋内退避又は避難が必要となるおそれのあるとき。 (イ) その他町長が必要と認めたとき。 (2) 災害対策本部の設置 ア 設置基準及び設置場所 町長は、次に掲げる状況になったとき、立科町災害対策本部を町役場庁舎内に設置する。 (ア) 原子力事業所の事故により放射性物質又は放射線の影響が広範囲に及び、町内において原子力緊急事態に伴う屋内退避又は避難が必要となったとき。 (イ) その他町長が必要と認めたとき。 イ 組織及び所管事務 第2編第2章第1節「非常参集職員の活動」に定めるところによる。 ウ 災害対策本部の廃止 おおむね次の基準による。 (ア) 町内において屋内退避又は避難の必要がなくなったとき。 (イ) 町長が、原子力災害に関する対策の必要がなくなったと認めたとき。 4 モニタリング等 原子力事業所の事故により放射性物質又は放射線の影響が広範囲に及び、町内において屋内退避又は避難が必要となるおそれのあるときは、次の対応を行う。 (1) 災害時のモニタリング 町は、必要に応じてモニタリングを実施するとともに、結果を町ホームページ等で公表する。 (2) 放射能濃度の測定 ア 町は、必要に応じて水道水、降下物、下水等汚泥、廃棄物焼却灰、流通食品、農林畜産物、農地用土壌、家畜用飼料、肥料等の放射能濃度の測定を実施するとともに、結果を町ホームページ等で公表する。 イ 町は、県が実施する測定が円滑に行われるよう協力する。 5 健康被害防止対策 町は、必要に応じて人体に係るスクリーニング及び除染、医薬品の確保を行うとともに、住民に対し、健康相談窓口を設置する。 6 住民等への的確な情報伝達 (1) 住民等への情報伝達活動 ア 町は、県と連携し、住民等に対する情報提供及び広報を多様な媒体を活用して迅速かつ的確に行う。 情報提供及び広報に当たっては、要配慮者、一時滞在者等に情報が伝わるよう配慮するとともに、県や原子力事業者との情報の一元化を図り、情報の空白時間がないよう定期的な情報提供に努める。 イ 町長は、報道機関を通じて原子力災害に関する広報活動を行う必要があると認めるときは、佐久地域振興局を経由して、県に対し、報道機関への放送要請を依頼する。 (2) 住民等からの問い合わせに対する対応 町は、必要に応じて放射線に関する健康相談、食品の安全等に関する相談、農林畜産物の生産等に関する相談等に対応する窓口を設置して、速やかに住民等からの問い合わせに対応する。 7 屋内退避、避難誘導等の防護活動 (1) 屋内退避及び避難誘導 ア 町は、町内において原子力緊急事態が宣言され原災法第15条第3項に基づき内閣総理大臣から屋内退避又は避難に関する指示があったときは、住民等に対し次の方法等で情報を提供する。 (ア) CATV、ホームページ、広報車及び有線放送等による広報活動 (イ) 町教育委員会等を通じた小・中学校への連絡 (ウ) 報道機関を通じたラジオ、テレビ、新聞などによる報道 (エ) 警察署・駐在所等からの情報提供、パトロールカーによる巡回、広報活動 (オ) 消防本部の広報車等による広報活動 (カ) 電気・ガス・通信事業者、各種団体の協力による広報活動 イ 町長は、内閣総理大臣から屋内退避若しくは避難に関する指示があったとき、又は原子力緊急事態宣言があったときから原子力緊急事態解除宣言があるまでの間において住民の生命又は身体を災害から保護し、その他災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、住民等に対する屋内退避又は避難の指示の措置を講ずる。 (ア) 屋内退避対象地域の住民に対して、自宅等の屋内に退避するなど、必要な指示を行う。必要に応じてあらかじめ指定された施設以外の施設についても、災害に対する安全性を確認し、かつ、管理者の同意を得た上で、退避所又は避難所を開設する。 (イ) 避難誘導に当たっては、要配慮者とその付添人の避難を優先する。特に放射線の影響を受けやすい妊婦、児童、乳幼児に配慮する。 (ウ) 退避・避難のための立退きの指示を行った場合は、警察、消防等と協力し、住民等の退避・避難状況を的確に把握する。 (エ) 退避所又は避難所の開設に当たっては、退避所又は避難所ごとに避難者の早期把握に努めるとともに、情報の伝達、食料、飲料水等の配布等について避難者、住民、自主防災組織等の協力を得て、円滑な運営管理を図る。 なお、「原子力災害対策指針(最新改定日 令和2年10月28日)」で示されている屋内退避及び避難等に関する指標は次の表のとおり。
(注1)「初期設定値」とは、緊急事態当初に用いる値であり、地上沈着した放射性核種組成が明確になった時点で必要な場合には改定される。 (注2)実際の適用に当たっては、空間放射線量率計測機器の設置場所における線量率と地上1mでの線量率との差異を考慮して、判断基準の値を補正する必要がある。 (注3)「地域生産物」とは、放出された放射性物質により直接汚染される野外で生産された食品であって、数週間以内に消費されるもの(例えば、野菜、該当地域の牧草を食べた牛の乳)をいう。 (注4)「一時移転」とは、緊急の避難が必要な場合と比較して空間放射線量率は低い地域ではあるが、日常生活を継続した場合の無用の被ばくを低減するため、一定期間のうちに当該地域から離れるために実施する措置をいう。 (2) 広域避難活動 ア 町は、町の区域を越えて避難を行う必要が生じたときは、他の市町村に対し受入先の供与及びその他災害救助の実施に協力するよう要請するとともに、県と連携し、避難先及び輸送ルートの調整を行う。 イ 町は、避難者の把握、住民等の避難先の指定を行い、あらかじめ定めた避難輸送方法等により避難させる。 ウ 他市町村から避難者の受入れの要請を受けたときは、あらかじめ定めた避難所を開設するとともに、必要な災害救助を実施する。 エ 町は、千曲バス㈱、諏訪バス㈱、自衛隊等と連携し、避難者の輸送を行う。 (3) 交通の規制及び立入制限等の措置 県は、市町村長が屋内退避又は避難を指示した区域について、外部から車両等が進入しないよう、交通の規制及び立入制限等必要な措置をとるよう関係機関に要請する。 8 緊急輸送活動 町は、次のとおり緊急輸送体制の確立を図る。 (1) 町は、県と連携し、緊急輸送の円滑な実施を確保する。 (2) 町は、人員、車両等に不足が生じたときは、県を通じて、次表の関係機関に支援を要請するとともに、必要に応じて隣接県に対しても支援を要請する。
9 飲料水・飲食物の摂取制限等 (1) 飲料水、飲食物の摂取制限 ア 県は、国の指示、要請及び県が実施する災害時モニタリングの結果に基づき、原子力規制委員会及び厚生労働省が示す飲食物摂取制限に関する指標を超え、又は超えるおそれがあると認められる場合は、汚染水源の使用禁止、汚染飲料水の飲用禁止、汚染飲食物の摂取制限等必要な措置を関係市町村又は水道事業者に指示又は要請する。 イ 町又は水道事業者は、国及び県からの指示、要請があったとき又は放射線被ばくから住民を防護するために必要があると判断するときは、汚染水源の使用禁止、汚染飲料水の飲用禁止、汚染飲食物の摂取制限等必要な措置を行う。 (2) 農林産物の採取及び出荷制限 ア 県は、国の指示及び要請に基づき、農林畜水産物の生産者、出荷機関及び市場の責任者等に汚染農林畜水産物の採取の禁止、出荷制限等必要な措置を自ら行うか、関係市町村に指示する。 イ 町は、国及び県からの指示があったとき又は放射線被ばくから住民を防護するために必要があると判断するときは、農林畜産物の生産者、出荷機関及び市場の責任者等に汚染農林畜産物の採取の禁止、出荷制限等必要な措置をとる。 (3) 経口摂取による被ばく影響を防止するため、飲食物の摂取を制限する際の基準
(「原子力災害対策指針(令和2年10月28日)」より)
(厚生労働省省令及び告示より) 10 県外からの避難者の受入れ活動 (1) 避難者の受入れ 町は、県と協力し、県境を越えて避難する者が発生した都道府県(以下「避難元都道府県」という。)に対する受入れ活動を次のとおり実施する。なお、県外からの避難者の受入れについては、風水害、地震など全ての災害においても準用するものとし、具体的な活動については、災害の状況により適切に判断することとする。 ア 緊急的な一時受入れ 町は、県から要請を受けたときは、避難元都道府県に対し、町の保有する施設を一時的な避難所として、当分の間提供する。なお、受入れに当たっては、要配慮者及びその家族を優先する。 イ 短期的な避難者の受入れ 町は、県から要請を受けたときは、避難元都道府県に対し必要に応じて次の対応を行う。 (ア) 県から被災自治体の避難者受入れ要請があったときは、まず緊急的な一時受入れと同様に、町の施設で対応する。 (イ) (ア)による受入れが困難なときは、町内の旅館・ホテル等を町が借り上げて避難所とする。 ウ 中期的な避難者の受入れ 町は、県から要請を受けたときは、避難元都道府県に対し必要に応じて次の対応を行う。 (ア) 避難者に対しては、町営住宅への受入れを行う。 (イ) 民間賃貸住宅を町が借り上げ、応急仮設住宅として提供する。 (ウ) 長期的に町に居住する意向のある者については、住宅、仕事等の相談に対応するなど、定住支援を行う。 (2) 避難者の生活支援及び情報提供 ア 町は、県及び避難元都道府県等と連携し、町内に避難を希望する避難者に対して、住まい、生活、医療、教育、介護などの多様なニーズを把握し、必要な支援につなげる。 イ 町は、県と連携し、避難者に関する情報を活用し、避難者に対し避難元市町村からの情報を提供するとともに、避難者支援に関する情報を提供する。 |