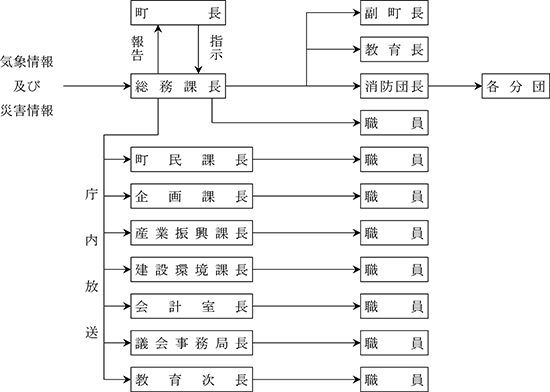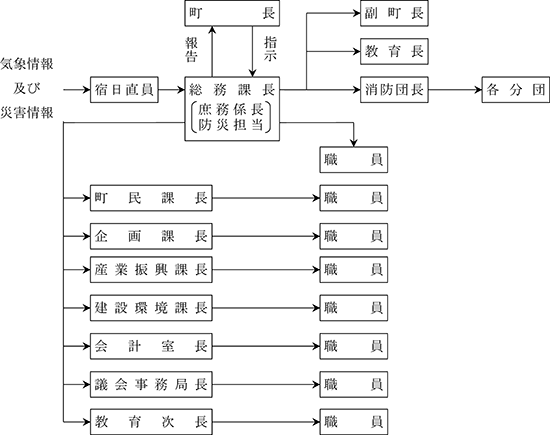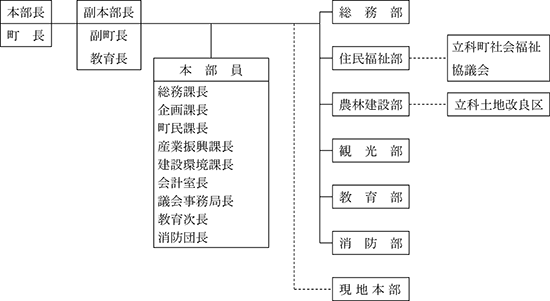|
〔全 部(全課等)〕
町は、町内に災害が発生し又は発生するおそれがある場合は、災害応急対策を迅速かつ強力に推進するため、法令及び防災に関する計画の定めるところによってその活動体制に万全を期するものとする。
この場合において、それぞれの防災関係機関は、その組織及び機能のすべてをあげて災害応急対策活動に協力するものとする。
1 職員動員配備体制
災害応急対策に対処するため、状況下に応じ次の配備体制をとる。
| 配備区分 |
活動開始基準 |
活動内容 |
活動期間 |
第 一 次
警戒配備
|
○暴風雪・大雪警報、暴風・大雨・洪水警報が発表されたとき。
○大雨・洪水・大雪・強風・風雪・雷注意報が発表され、災害が発生するおそれがあるときで、町長が必要と認めたとき。 |
○事態に対処するため、情報収集・伝達を行う。
|
活動開始基準に該当したときから次に該当するときまで。
○警報等が解除されたとき。
○町長が配備の必要がないと認めたとき。
○他の体制に移行したとき。 |
第 二 次
警戒配備
|
○第一次警戒配備の状況下で町長が必要と認めたとき。
○土砂災害警戒情報が発表されたとき。
|
○災害発生前の体制で、各部局連絡網の確認、情報収集等を行う。
○災害関係課等の職員で情報収集活動が円滑に行いうる体制とする。
○各部局所管する危険箇所等のパトロールを行う。 |
活動開始基準に該当したときから次に該当するときまで。
○警報等が解除されたとき。
○町長が配備の必要がないと認めたとき。
○他の体制に移行したとき。
|
非常配備
|
○局地的な災害が発生したとき。
○激甚な災害が発生するおそれのあるとき。
○町全域にわたり大規模な災害が発生するおそれがある場合で、町長が指示したとき。 |
○広域的又は大規模な災害に対処する体制とし、状況に応じて緊急配備に移行し得る体制とする。
|
活動開始基準に該当したときから次に該当するときまで。
○町長が配備の必要がないと認めたとき。
○他の体制に移行したとき。
|
| 緊急配備 |
○町全域にわたり大規模な災害が発生した場合で、町長が指示したとき。
○気象特別警報が発表されたとき。 |
○町の組織及び機能のすべてをあげて対処する体制とし、各所属職員全員を配備する。
○事態の推移により必要な人員による体制を構築する。 |
活動開始基準に該当したときから次に該当するときまで。
○町長が指示したとき。
○他の体制に移行したとき。 |
(注) 活動(配備)時間は次の二交代制とする。
① 午前8時30分から午後5時15分まで
② 午後5時15分から翌朝の午前8時30分まで
ただし、第一次警戒配備については次のとおりとする。
・大雨注意報の発表に伴う配備は、平日の午後5時15分から翌朝午前8時30分までと、週休日及び祝日の終日を自宅待機とする。
・暴風雪・大雪警報の発表に伴う配備は、平日の午後8時から翌朝午前8時30分までと、週休日及び祝日の終日を自宅待機とする。
2 各体制ごとの配備要員
部 名 |
所 属 課 等 |
第一次
警戒配備 |
第二次
警戒配備 |
非常配備 |
緊急配備 |
総 務 部 |
総務課 |
4 |
4 |
全職員の半数 |
全職員 |
企画課 |
1 |
2 |
全職員の半数 |
全職員 |
議会事務局 |
|
|
全職員の半数 |
全職員 |
会計室 |
|
|
全職員の半数 |
全職員 |
住民福祉部 |
町民課 |
|
1 |
全職員の半数 |
全職員 |
農林建設部 |
産業振興課 |
1 |
2 |
全職員の半数 |
全職員 |
建設環境課 |
1 |
2 |
全職員の半数 |
全職員 |
観 光 部 |
産業振興課 |
|
1 |
全職員の半数 |
全職員 |
教 育 部 |
教育委員会 |
|
1 |
全職員の半数 |
全職員 |
消 防 部 |
消防団 |
|
16 |
32 |
全職員 |
※ 第一次警戒配備及び第二次警戒配備において、町長が必要と認めたとき、配備要員を増員する。対応する職員は、各担当課長等の判断による指名された職員とする。
3 配備指令の伝達及び配備担当者の招集
(1) 伝達系統・方法
配備指令及び配備担当者の招集の伝達は、次の方法で行う。
○勤務時間内
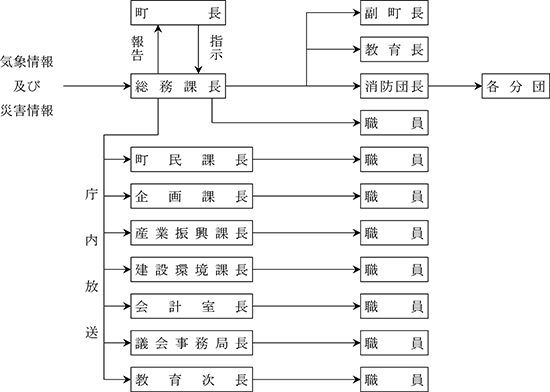
○勤務時間外
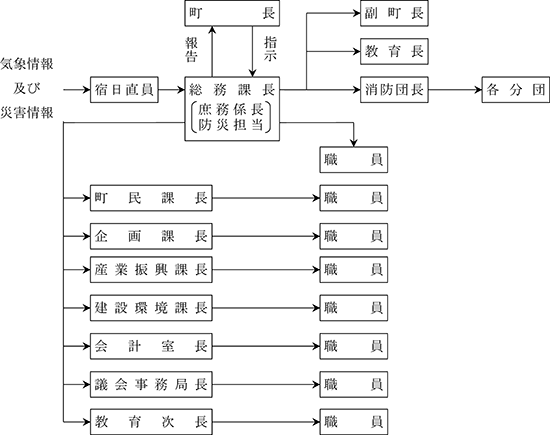
(2) 配備担当者の決定
関係課長は、あらかじめ配備担当者並びにその連絡方法を定めておく。
(3) 参集時の留意事項
参集時、職員は、次の点に留意する。
| 服 装 |
・応急活動ができる服装とし、安全な靴、帽子又はヘルメット、手袋 |
| 携 行 品 |
・筆記具 ・携帯ライト ・携帯ラジオ ・タオル
・飲料水、食料 ・応急医薬品等 |
| 緊 急 措 置 |
・参集途上において、火災の発生、又は人身事故に遭遇したときは、住民の協力を求め、消火・救急・救助活動を行う。ただし、現場に消防職員がいるときは、その活動を引継ぎ、役場庁舎に直行する。 |
| 被害状況報告 |
・幹線道路等の状況
・建物の倒壊、損傷の状況
・火災の発生、消火活動の状況
・被災者、救助活動の状況
・ライフラインの状況 |
4 災害対策本部の設置
(1) 設置基準
町長は、町内全域にわたって災害が発生したとき、又は局地的な災害であっても、甚大な被害を受けたときには、立科町災害対策本部(以下「町本部」という。)を町役場庁舎内に設置する。ただし、庁舎が被災して使用不能になった場合には、白樺高原総合観光センターに設置する。
なお、町庁舎は、防災拠点の中枢である。その機能が十分果たせるよう、非常用発電機等の設備の維持管理及び飲料水や食料の確保に努める。
(2) 災害対策本部の組織
町本部の組織等は、「立科町災害対策本部条例」(資料1-2参照)に定めるところによる。
ア 本部長(町長)
本部長は、本部の事務を総括し、本部職員を指揮監督する。
イ 副本部長(副町長、教育長)
副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。
ウ 本部員(各課長、教育次長、消防団長)
本部員は、本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従事する。
エ 本部会議
(ア) 本部会議は、本部長、副本部長、本部員をもって構成し、災害対策に関する重要事項を協議決定する。
(イ) 本部会議は、本部長が招集し、主宰する。
(ウ) 本部員は、災害対策に関し、本部会議に付議する必要があると認めるときは、本部会議の開催を要請することができる。
(3) 災害対策本部の廃止
本部長は、町内の地域において、災害が拡大するおそれがなくなった場合で、次に掲げる状況から災害応急対策がおおむね完了したと判断できるときは、本部を廃止する。
ア 災害救助法による応急救助が完了したとき。
イ 公的避難所の廃止、仮設住宅の整備の完了等当面の日常生活の場が確保されたとき。
ウ 災害援護資金等、各種の公的資金制度等による被災者支援が講じられたとき。
エ 被害数値がおおむね確定したとき。
オ 災害応急対策から災害復旧対策への移行が判断できるとき。
(4) 県等への設置・廃止の通知公表
町災害対策本部を設置・廃止したときは、直ちにその旨を次の区分により通知及び公表を行う。
災害対策本部設置・廃止の通知区分
| 通知及び公表先 |
通知及び公表の方法 |
責 任 者 |
各 課
住 民
県 本 部
地 方 部
|
庁 内 放 送
防災行政無線、たてしなび、CATV、広報車等
県 防 災 無 線
県 防 災 無 線 |
総務課長
総務課長
総務課長
総務課長 |
5 現地災害対策本部の設置
災害の状況により本部長が必要と認めるときは、災害現場付近に現地災害対策本部を設置し、迅速かつ的確な対応活動の指揮を行うこととする。
(1) 現地災害対策本部の開設
ア 本部長は職員のうちから現地災害対策本部長及び現地災害対策本部員を指名し、現地へ派遣する。
イ 現地災害対策本部を開設したときは、立看板、のぼり等で表示する。
ウ 現地災害対策本部には、立科町防災行政無線移動局、NTT仮設電話等の通信設備を設置して、常に災害対策本部と緊密な連絡をとるものとする。
(2) 現地災害対策本部の責務
ア 災害の状況、災害現場出動部隊の活動状況を的確に把握し、住民の安全確保、被害の拡大防止をする。
イ 出動機関相互間の指揮及び情報連絡体制の総括を図る。
ウ 入手した情報を逐次災害対策本部へ報告する。
災害対策本部組織図
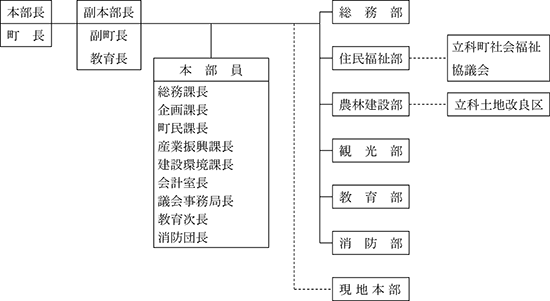
災害対策本部組織の担当
| 対 策 部 |
担 当 部 署 |
| 総 務 部 |
総務課 企画課 議会事務局 会計室 |
| 住民福祉部 |
町民課 |
| 農林建設部 |
産業振興課 建設環境課 |
| 観 光 部 |
産業振興課 |
| 教 育 部 |
教育委員会 |
| 消 防 部 |
消防団 |
災害対策本部事務分掌
部 名
(◎部長、○副部長) |
事 務 分 掌 |
| 総 務 部
◎総務課長
○企画課長
○議会事務局長
○会計室長 |
・本部会議に関すること。
・各部の総合調整及び連絡に関すること。
・職員の非常参集及び動員・配置計画に関すること。
・気象情報の受理、伝達に関すること。
・被害状況調査の取りまとめ及び県への報告に関すること。
・自衛隊の災害派遣要請に関すること。
・県及び市町村等への応援要請に関すること。
・ヘリコプターの派遣要請に関すること。
・災害対策の予算措置に関すること。
・災害関係経費の出納に関すること。
・義援金の受付、保管、配分に関すること。
・車両の配置及び借り上げに関すること。
・災害に関する各種広報に関すること。
・報道機関への情報提供に関すること。
・避難の勧告・指示及び避難所の開設に関すること。
・り災証明書の発行に関すること。
・商業施設及び生産品の被害状況調査に関すること。
|
| 住民福祉部
◎町民課長 |
・避難行動要支援者の安否確認及び避難支援に関すること。
・被災者の安否問い合わせ及び被災者名簿の作成に関すること。
・被災者相談窓口の設置に関すること。
・遺体の処理及び埋葬に関すること。
・避難所の運営・管理に関すること。
・社会福祉施設の保全及び応急措置に関すること。
・日赤奉仕団、社会福祉協議会、その他社会福祉団体との連絡及び協力要請に関すること。
・ボランティアの受入れに関すること。
・応急食料の調達、供給に関すること。
・炊き出しに関すること。
・生活必需品の調達、供給に関すること。
・義援物資の受付、保管、配分に関すること。 |
| 農林建設部
◎建設環境課長
○産業振興課長 |
・農産物の災害対策及び被害状況調査に関すること。
・災害時における病虫害の防除に関すること。
・農地及び農業用施設の災害対策に関すること。
・家畜等の被害状況調査に関すること。
・死亡獣畜の処理指導に関すること。
・造林、林業施設及び林産物の災害対策に関すること。
・農業用水路の被害状況調査に関すること。
・道路・橋梁の保全及び応急対策に関すること。
・障害物の除去及び交通規制等応急交通対策に関すること。
・土砂災害等の応急対策に関すること。
・河川、水路その他の保全及び応急対策に関すること。
・応急仮設住宅の建設に関すること。
・水道施設の被害状況調査及び応急復旧に関すること。
・飲料水の確保に関すること。
・下水道施設の被害状況調査及び応急復旧に関すること。
・災害時の防疫、感染症患者の収容及び公衆衛生に関すること。
・ごみ、し尿処理に関すること。 |
| 観 光 部
◎産業振興課長 |
・観光施設の被害状況調査及び応急復旧に関すること。
・観光客の安全確保に関すること。
・風評害対策に関すること。
|
| 教 育 部
◎教育次長
|
・学校施設の被害状況調査及び応急対策に関すること。
・保育園児の安全確保に関すること。
・児童生徒等の安全確保に関すること。
・被災保育園及び園児の応急保育対策に関すること。
・被災学校及び児童生徒等の応急教育対策に関すること。
・PTA等教育関係団体との連絡及び協力要請に関すること。
・災害時における教材器具の調達に関すること。
・文化財の被害状況調査及び応急対策に関すること。
・社会教育施設の被害状況調査及び応急対策に関すること。
・施設利用者の安全確保に関すること。 |
| 消 防 部
◎消防団長
|
・消防活動に関すること。
・河川等水害危険区域の巡視、警戒及び応急復旧対策に関すること。
・避難誘導に関すること。
・人命救助に関すること。
・行方不明者の捜索及び遺体の処理に関すること。 |
|