|
第3節 災害情報の収集・連絡活動 |
|
〔全 部(全課等)〕 災害が発生した場合、町及び各防災関係機関(調査責任機関)は直ちに災害時における被害状況調査体制を取り、迅速・的確な被害状況の調査を行う。 1 報告の種別 (1) 概況速報 災害が発生したとき、災害対策本部を設置したとき、又はその他異常と思われる事態が発生したときは直ちにその概況を報告する。 (2) 被害中間報告 被害状況を収集し、逐次報告するとともに、先に報告した事項に変更のあった場合はその都度変更の報告をする。 (3) 被害確定報告 同一の災害に対する被害調査が終了し、被害が確定したときに報告する。 2 被害状況等の調査と調査責任機関 (1) 被害状況の調査は、町調査担当課が関係機関及び団体の協力を得て実施する。調査に当たっては関係各課は相互に連絡を密にし、正確な情報の把握に努めるものとする。 なお、被害が甚大であり、町において被害調査が実施できないときは県現地機関等に応援を求め行う。 (2) 町は、自らの対応力のみでは十分な災害対策を講ずることができないような災害が発生したときは、速やかに他市町村の応援を求めるなどして情報を収集し、被害の詳細を迅速に県に報告するよう努める。 (3) 特に行方不明者の数については、捜索・救助体制の検討に必要な情報であるため、住民登録の有無にかかわらず、町の区域内で行方不明となった者について、県警察本部の協力に基づき正確な情報の収集に努める。また、要救助者の迅速な把握のため、安否不明者についても、関係機関の協力を得て、積極的に情報収集を行う。 3 被害状況等報告内容の基準 この計画における被害の程度区分の判定は、法令等に特別の定めがある場合を除くほか、資料8-2のとおりとする。 4 災害情報の収集・連絡系統 (1) 被害報告等 ア 町は、あらかじめ定められた情報収集連絡体制をとり、町が調査機関として定められている事項については被害状況等を調査の上、被害状況等の部門別及び被害種別の報告様式により、県現地機関等に報告する。 なお、災害発生後の第一報(即報)は、原則として、覚知後30分以内で可能な限り早く、分かる範囲で報告する。 イ 町における体制のみでは、円滑な情報収集連絡の実施が困難であると認められる場合は地域振興局長に応援を求める。 ウ 次の場合は、消防庁に対して直接報告する。 (ア) 県に報告できない場合 災害対策本部を設置し、又は、災害の状況及びそれが及ぼす社会的影響等からみて、特に報告の必要があると認められる程度の災害が発生した場合において、県との通信手段が途絶するなど、被災状況により県への報告ができないとき。ただし、この場合にも町は県との連絡確保に努め、連絡が取れるようになった後は、県に対して報告する。 (イ) 消防庁に報告すべき災害が発生した場合 火災・災害等即報要領(昭和59年消防災第267号)の「直接即報基準」に該当する火災、災害等を覚知した場合、町及び消防本部は、第一報を県に対してだけでなく、消防庁に対しても報告する。この場合において、消防庁長官から要請があった場合については、第一報後の報告についても、引き続き消防庁に対しても行う。 連絡先
○長野県危機管理部
○消防庁
(ウ) (ア)又は(イ)に定める災害になるおそれのある災害 (2) 地震情報 気象庁地震火山部及び長野地方気象台は、地震発生後、震度速報、震源・震度に関する情報、各地の震度に関する情報を発表、一斉伝達する。 (3) 水防情報 県水防本部、建設事務所、雨量(水位)観測員は、それぞれ雨量、水位を関係部署に通報する。 ◎立科町の災害情報連絡系統図 (1) 概況速報 長野県防災情報システム クロノロジーを使用 町は、人的被害、住家被害に関するもの及び集落の孤立を伴う交通情報を中心に報告する。 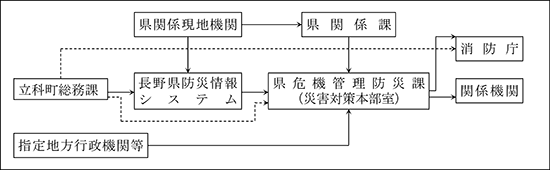 (2) 人的及び住家の被害状況報告 高齢者等避難・避難指示・緊急安全確保等避難状況報告 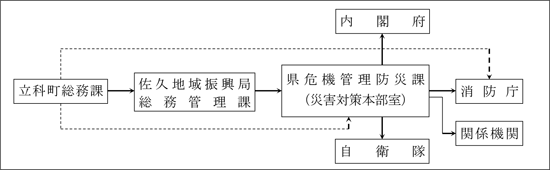 ※ 行方不明者として把握した者が、他の市町村に住民登録を行っていることが判明した場合には、当該登録地の市町村(外国人のうち、旅行者など短期滞在の者は直接又は必要に応じ外務省を通じて在京大使館等)又は県危機管理防災課(災害対策本部)に連絡する。 (3) 社会福祉施設被害状況報告 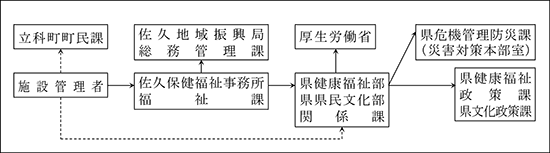 (4) 農業関係被害状況報告 ア 農・畜・水産業被害状況報告  イ 農地・農業用施設被害状況報告 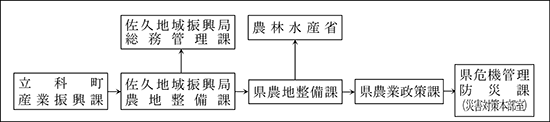 ウ 農業集落排水施設被害状況報告 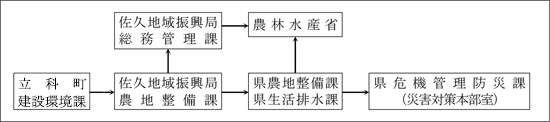 (5) 林業関係被害状況報告 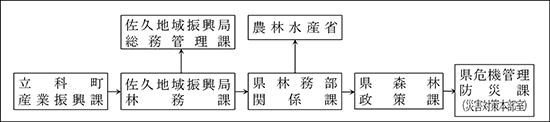 (6) 土木関係被害状況報告 ア 県管理河川の氾濫箇所 地図又はGISによる 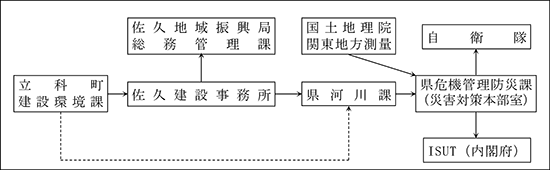 イ 公共土木施設被害状況報告等 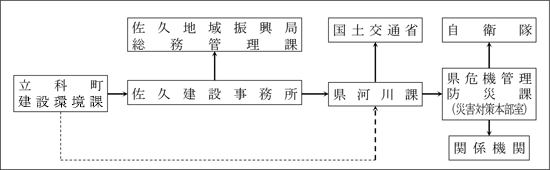 ウ 土砂災害等による被害報告 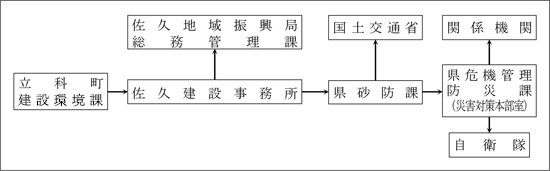 (7) 都市施設被害状況報告 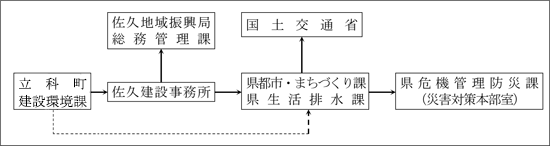 (8) 水道施設被害状況報告 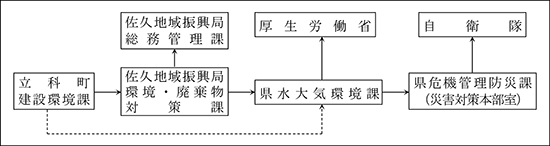 (9) 廃棄物処理施設被害状況報告 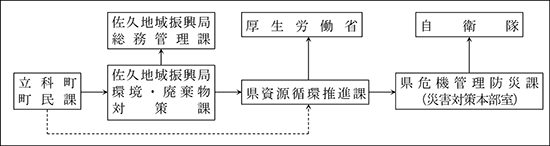 (10) 感染症関係報告 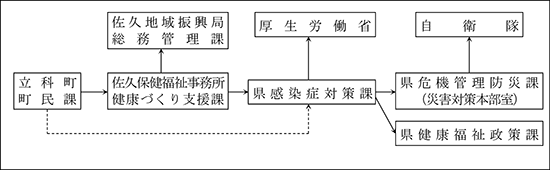 (11) 医療施設関係被害状況報告  (12) 商工関係被害状況報告 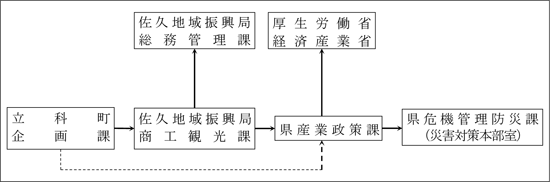 (13) 観光施設被害状況報告 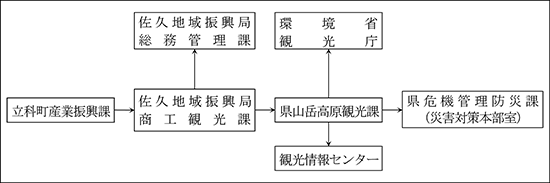 (14) 教育関係被害状況報告 ア 町施設  イ 県施設 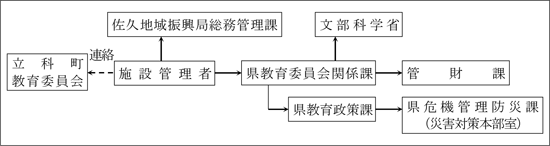 ウ 文化財 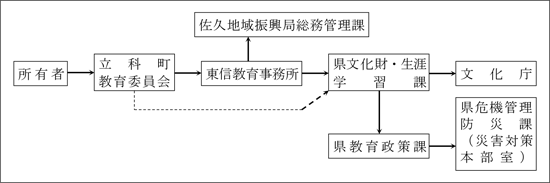 (15) 町有財産  (16) 火災即報  (17) 火災等即報(危険物に係る事故) 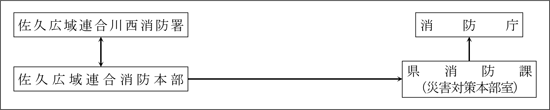 (18) 警察調査被害状況報告 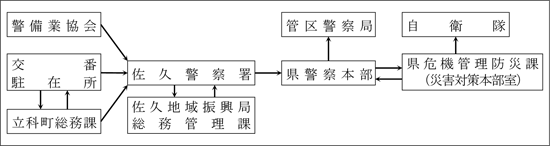 (19) 水防情報 雨量・水位の通報 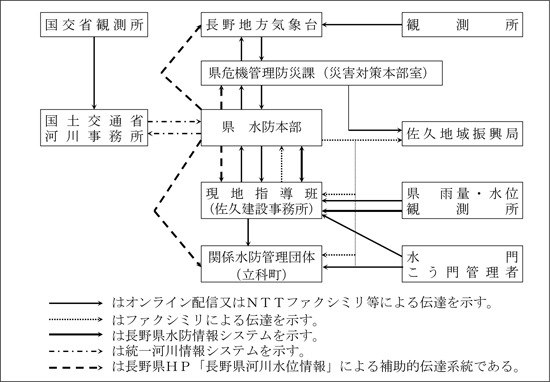 5 通信手段の確保 (1) 災害情報の共有ならびに通信手段確保のため、防災行政無線、たてしなび、CATV等及び県防災行政無線の活用を図る。 (2) 無線通信施設が被災した場合には、町職員と保守業者により復旧活動を行い、通信の確保に努める。 (3) 停電が発生した場合は、予備電源を確保して応急の対応を図り、通信施設への復電まで長期間が予想される場合には、燃料の調達、供給を図る。 (4) 災害時用通信手段なども使用不能又は困難となった場合には、非常通信によるものとし、近隣の使用可能な通信手段を持つ機関に通信を依頼する。 (5) 災害情報の共有ならびに通信手段確保のため可搬型移動無線、携帯電話等移動無線機器の活用を図る。 (6) 必要に応じて、信越総合通信局に対し、災害対策用移動通信機器、災害対策用移動電源車の貸出要請を行う。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||