|
第10節 緊急輸送計画 |
|
〔総務課・建設環境課〕 大規模災害発生時には、救急救助活動、消火活動、各種救援活動など、人命救助と被災者の生活確保及び早期復旧のために、よりスムーズな人・物の流れが必要とされることから、こうした緊急輸送業務について、緊急交通路の確保と輸送力の確保に関し、迅速に対応できる体制を平常時から確立するとともに、緊急通行車両の事前確認等を行い、災害による交通障害を未然に防止し、障害発生に対しても適切に対処し得る事前対策を確立する。 1 緊急交通路の確保 (1) 緊急輸送路の指定・整備 緊急輸送路の指定及び整備は、県が次のように実施する。 ア 「緊急交通路交通規制対象予定道路」を指定し、大規模災害時の総合交通規制について隣接県警察と協議のうえ、協定を締結する。 イ 「一次緊急輸送路」、「二次緊急輸送路」を定めて、緊急度の高い箇所から順次整備し、災害に強い道路交通網整備を推進する。 (2) 緊急交通路接続道路の確保 町は、警察署と協議のうえ、地域の実情に合った区域内の交通確保計画を策定する。この場合、県の指定する「緊急交通路交通規制対象予定道路」と物資輸送拠点、災害対策用ヘリポート、避難所等との接続道路を確保するため、県、警察署との連携のもと、適切な幅員の整備に努める。 2 緊急用ヘリポート及び物資輸送拠点の確保 災害時の輸送の拠点となるヘリポート及び物資輸送拠点を指定し、必要に応じて施設等の整備を行う。 (1) 拠点ヘリポート 権現山運動公園多目的グラウンド (2) 物資輸送拠点 権現山運動公園多目的グラウンド 3 輸送体制の整備 (1) 管内の輸送事業者と連絡を密にし、発災時の協力体制を確保しておく。 (2) 必要に応じ、緊急輸送に係る調整業務等への運送事業者等の参加、物資の輸送拠点における運送事業者等を主体とした業務の実施、物資の輸送拠点として運送事業者等の施設を活用するための体制整備を図る。この際、災害時に物資の輸送拠点から指定避難所等までの輸送手段を含めた体制が速やかに確保できるよう、あらかじめ、適切な物資の輸送拠点を選定しておくよう努める。 (3) 物資の調達・輸送に必要となる情報項目・単位の整理による発注方法の標準化、物資の輸送拠点となる民間施設への非常用電源、燃料貯蔵設備及び非常用通信設備の設置に係る支援、緊急通行車両等への優先的な燃料供給等の環境整備を図る。なお、燃料については、あらかじめ、石油販売業者と、燃料の優先供給について協定の締結を推進するとともに、平時から受注機会の増大などに配慮するよう努める。 (4) 輸送協定を締結した民間事業者等の車両については、緊急通行車両標章交付のための事前届出制度が適用され、発災後、当該車両に対して緊急通行車両標章を円滑に交付されることとなることから、民間事業者等に対して周知を行うとともに、自らも事前届出を積極的にするなど、その普及を図る。 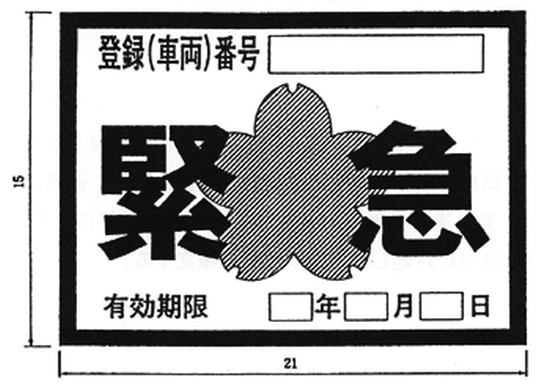 備考 1 色彩は、記号を黄色、縁及び「緊急」の文字を赤色、「登録(車両)番号」、「有効期限」、「年」、「月」及び「日」の文字を黒色、登録(車両)番号並びに年、月及び日を表示する部分を白色、地を銀色とする。 2 記号の部分に、表面の画像が光の反射角度に応じて変化する措置を施す。 3 図示の長さの単位は、センチメートルとする。 4 障害物の処理体制の整備 (1) 森林組合等林業関係団体と倒木処理について調整し、体制を整備する。 (2) 立科町建設業連合会と「災害時の応急措置に関する協定書」(資料2-9参照)に基づき、平常時から協議を行う。 (3) 障害物の一時集積場所をあらかじめ定めておく。 |